1998年 春・夏 街 灯
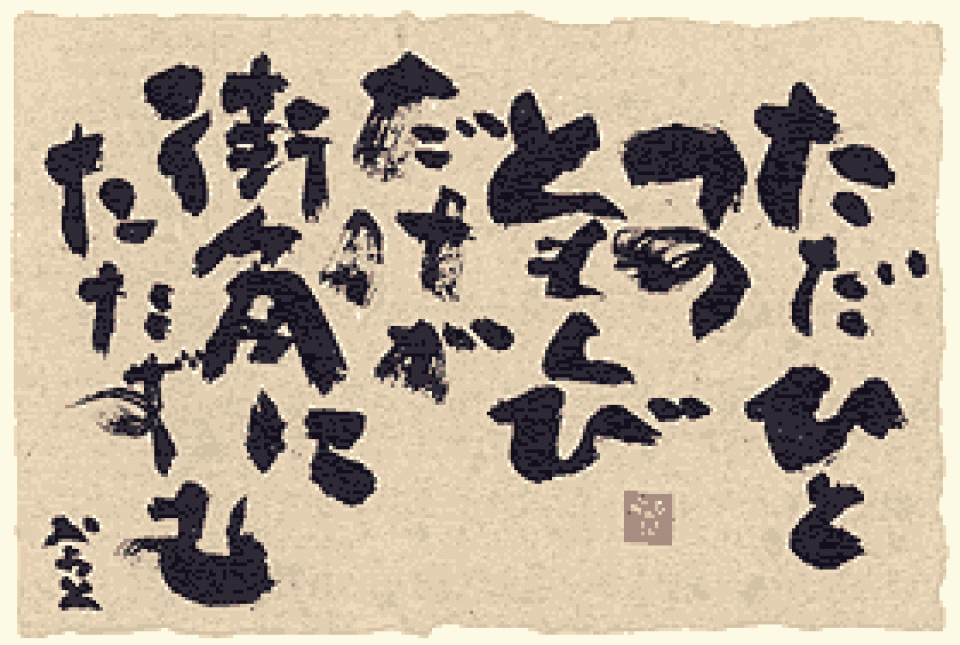
レニングラード(今はサンクト・ベテルスブルグ)は美しい街だ。ネバ河のいくつもの大きな流れが素晴らしい。古い建物が河岸に黄金の輝きを放つ風景は、他に例のないほどのスケールだ。けれど着いた日、私たちが入ったホテルは郊外の新しい建物。いかにも安普請で、ドアもうまく閉まらない。ソ連時代の奥行きの浅さがうかがわれてわびしい。それに街へ出るにはネバ河を越えていかなかればならない。
夜、夕食が終わったあと、同行したミュージシャンたちは、それでも出かけて行った。大都会の美しさを見ずにくすぶってはいられない。
私とマネージャーは、自重して残ったけれどもう一人出かけないサックスプレーヤーがいた。「コンサートに来た可愛い女性に、誘われているけれど言葉が出来ないからあきらめた」という。おとなしい彼の背中を何とか押してあげようと、ソ連に入ってから覚えた「街灯」という歌のメロディーを、彼に教え、これを口ずさめばきっともてるよ、と勇気づけ、
彼はしぶしぶ出かけて行った。
ところがその夜、深夜になっても誰も帰ってこない。マネージャーと二人、心配で心配で、あんなに皆を送り出すんじゃなかったと悔やんだ。次の日もコンサートがあるのに、何かあったら大変だ。
でも翌朝、皆それぞれ帰ってきた。「夜の十二時にネバ河の橋が上がってしまってホテルに帰れず大変だったんだよ」と。「それでどうしたの」と追及すると答えは各々曖昧だ。いいことでも何かあったのかな。
ちょうどそこへコンサートが好評で連続五回にあと二回、マチネーを増やせないかと言って来た。
私たちは「ホテルを街の中心にかえること」を条件にしようと全員一致。コンサートを仕切っているゴス・コンツェルトは「今は国際会議でどこも満杯、『コスイギン首相』でも無理だ」と言って来た。私たちはそれでもこの条件を主張しつづけた。
その夜、コンサート終了後、突然、引っ越し通告があり、「オクチャーブル(十月)」という一番古い有名なホテルに入ることになった。他の宿泊客を相部屋につめこんだらしい。国家が決めれば出来ない事のない国なんだな、とちょっと恐ろしい気もした。
翌々日は約束のマチネー公演、夜の部との間に劇場の中にあるキッチンで手料理をご馳走になることになった。コックさんは太った六十すぎのおばちゃん、焼き立ての黒パンにカルバッサ(ソーセージ)、茹でたじゃがいも、キャビヤにスープ。美味しくて美味しくて今も思い出す。前日までのホテルのレストランの料理のまずさ、メニューのすくなさにまいっていた私たちは大感激。
このおばちゃん、私の少しばかりのロシア語を褒めてくれて、私相手におしゃべりをいつまでも続ける。私が勝手に想像力を働かせて聞いたのは、息子のこと、自分の子供の頃のこと、革命のこと、のようだった。レニングラードのような都会では若い人の中にとってもクールでツンとした人が多く、そこにソ連型ロシア人の空気を感じたりしていたけれど、この人のように革命をくぐり抜けた人々には、ロシアの味と、生き抜いた歴史の重みのようなものがある。中学のころロシア・レストラン・スンガリーが出来てから触れあってきたロシア人たちと同じだ。
父は終生、ロシアを愛し、何度も何度もソ連を旅したけれど、いつも口癖のように言っていた。「ソ連なんてものは外面だけや、あいつらは皆ロシア人。何も変わってない。いっそ国の名前をもう一回ロシアにもどしたらええのになあ。」
「そんな馬鹿な」と私は笑ったけれど、ソ連が崩壊してあっさりと「ロシア」という国名がもどった時、父のこの言葉を思い出した。ちょうどその転換期にウラジオストックに滞在していた父は得意満面だった。
「それにしても驚いたのは、ソ連がなくなった途端に、軍人の集まる酒場に『エカテリーナ』や『ニコライ』の肖像画があるんだよ。『こんなもん隠しとったんか』と聞いたら『そんなことはない、新しく描かせたんだ』と言うんだが、そんなはずはない。あいつらはツアーの時代のロシアを捨てとらんかったんやな。」と父が言っていた。
あれから三十年以上が過ぎ、すっかりあの街も変わったことだろう。そう言えば「十月」と言う革命にちなんだホテル名も今は変わっているに違いない。
「街灯(ファナリ)を去年久し振りに歌って、サドコと「Tokiko Romantic」の中にレコーディングした。なつかしかった!
美しくて、幻想的だったレニングラードを今もありありと思い出す。
夜、夕食が終わったあと、同行したミュージシャンたちは、それでも出かけて行った。大都会の美しさを見ずにくすぶってはいられない。
私とマネージャーは、自重して残ったけれどもう一人出かけないサックスプレーヤーがいた。「コンサートに来た可愛い女性に、誘われているけれど言葉が出来ないからあきらめた」という。おとなしい彼の背中を何とか押してあげようと、ソ連に入ってから覚えた「街灯」という歌のメロディーを、彼に教え、これを口ずさめばきっともてるよ、と勇気づけ、
彼はしぶしぶ出かけて行った。
ところがその夜、深夜になっても誰も帰ってこない。マネージャーと二人、心配で心配で、あんなに皆を送り出すんじゃなかったと悔やんだ。次の日もコンサートがあるのに、何かあったら大変だ。
でも翌朝、皆それぞれ帰ってきた。「夜の十二時にネバ河の橋が上がってしまってホテルに帰れず大変だったんだよ」と。「それでどうしたの」と追及すると答えは各々曖昧だ。いいことでも何かあったのかな。
ちょうどそこへコンサートが好評で連続五回にあと二回、マチネーを増やせないかと言って来た。
私たちは「ホテルを街の中心にかえること」を条件にしようと全員一致。コンサートを仕切っているゴス・コンツェルトは「今は国際会議でどこも満杯、『コスイギン首相』でも無理だ」と言って来た。私たちはそれでもこの条件を主張しつづけた。
その夜、コンサート終了後、突然、引っ越し通告があり、「オクチャーブル(十月)」という一番古い有名なホテルに入ることになった。他の宿泊客を相部屋につめこんだらしい。国家が決めれば出来ない事のない国なんだな、とちょっと恐ろしい気もした。
翌々日は約束のマチネー公演、夜の部との間に劇場の中にあるキッチンで手料理をご馳走になることになった。コックさんは太った六十すぎのおばちゃん、焼き立ての黒パンにカルバッサ(ソーセージ)、茹でたじゃがいも、キャビヤにスープ。美味しくて美味しくて今も思い出す。前日までのホテルのレストランの料理のまずさ、メニューのすくなさにまいっていた私たちは大感激。
このおばちゃん、私の少しばかりのロシア語を褒めてくれて、私相手におしゃべりをいつまでも続ける。私が勝手に想像力を働かせて聞いたのは、息子のこと、自分の子供の頃のこと、革命のこと、のようだった。レニングラードのような都会では若い人の中にとってもクールでツンとした人が多く、そこにソ連型ロシア人の空気を感じたりしていたけれど、この人のように革命をくぐり抜けた人々には、ロシアの味と、生き抜いた歴史の重みのようなものがある。中学のころロシア・レストラン・スンガリーが出来てから触れあってきたロシア人たちと同じだ。
父は終生、ロシアを愛し、何度も何度もソ連を旅したけれど、いつも口癖のように言っていた。「ソ連なんてものは外面だけや、あいつらは皆ロシア人。何も変わってない。いっそ国の名前をもう一回ロシアにもどしたらええのになあ。」
「そんな馬鹿な」と私は笑ったけれど、ソ連が崩壊してあっさりと「ロシア」という国名がもどった時、父のこの言葉を思い出した。ちょうどその転換期にウラジオストックに滞在していた父は得意満面だった。
「それにしても驚いたのは、ソ連がなくなった途端に、軍人の集まる酒場に『エカテリーナ』や『ニコライ』の肖像画があるんだよ。『こんなもん隠しとったんか』と聞いたら『そんなことはない、新しく描かせたんだ』と言うんだが、そんなはずはない。あいつらはツアーの時代のロシアを捨てとらんかったんやな。」と父が言っていた。
あれから三十年以上が過ぎ、すっかりあの街も変わったことだろう。そう言えば「十月」と言う革命にちなんだホテル名も今は変わっているに違いない。
「街灯(ファナリ)を去年久し振りに歌って、サドコと「Tokiko Romantic」の中にレコーディングした。なつかしかった!
美しくて、幻想的だったレニングラードを今もありありと思い出す。

