1998年 秋 別れの朝
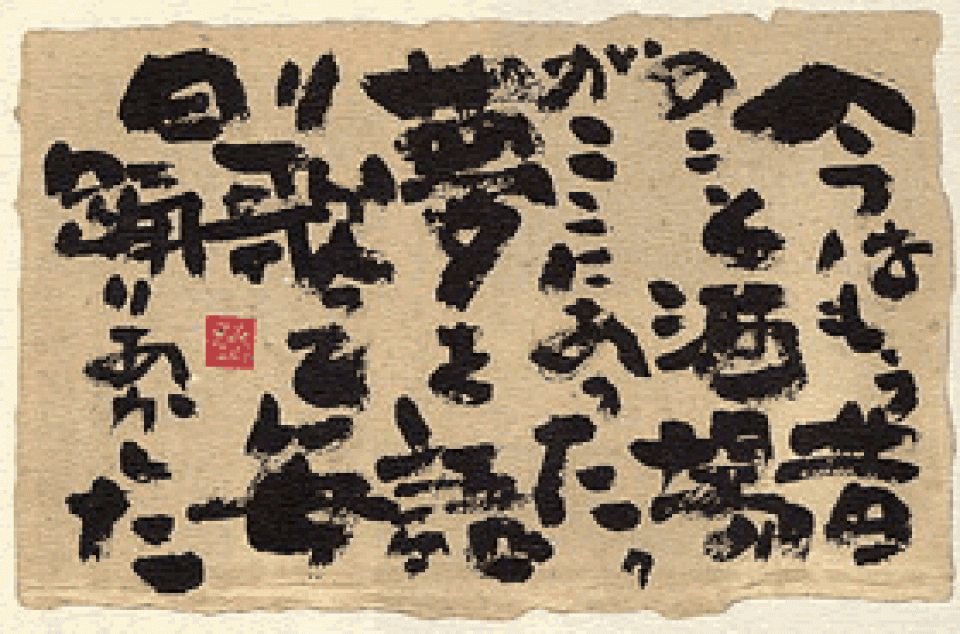
ソ連演奏旅行の最後は、黒海のほとりのスフミという街。ワインとコニャックの美味しいグルジアの避暑地。急に気がゆるんで海へと繰り出し、白い水着に身を包み、昼間はおおいに遊んだ。そこで夏休みで帰省している学生たちと仲良くなり、夜九時からのコンサートにさしつかえない午後のパーティーに行くことになった。
学生が案内してくれたアパートには20人近くの学生がいて、そこにはチェコの人やハンガリーの人やいろいろな学生がまじっていた。自由で西欧的でどうもソ連が嫌いな人たちらしく、私に「この国の歌なんか歌わなくてもいい。あなたはあなた自身の歌を歌ったほうがいい。僕たちはこの国の歌なんか嫌いなんだ」と、しきりに言って、大きなテープレコーダーでヨーロッパの電波からキャッチした音楽をガンガンかけて踊ったり、一緒に歌ったりしていた。一番人気はビートルズよりもアニマルズらしい。おもしろかったのは東欧のロックだった。シンプルなマイナーコードで、シャウトにはアメリカのロックにはないスゴ味があって、いまでもその音が耳の底に残っている。
あれは過激な学生たちだったのか、それともごく普通の人たちだったのかはわからない。けれど私を案内してくれた学生のひとりとホテルに戻ったときには大事件になっていた。私が単独に許可なく行動したことは、とんでもないことだったのだ。その学生も平謝りに謝って、それからは何度か逢いに来たのに、許可されずに帰ってしまうことが続いた。モスクワへ私が行く頃には、彼らもみんなモスクワにいるから、その時、電話して逢おうと約束していたのに、結局どの電話も意味不明の混線をおこして切れてしまうという結果になった。
実のところ、私はなにも知らなかったし、彼らも知っていたかどうかわからないけれど、ちょうどその頃、チェコ侵入があったのだ。プラハに戦車が突入し、日本では大ニュースだったはず。ソ連国内での報道がどうだったかは知る由もない。船で横浜に帰国したとき、新聞記者がドカドカと乗り込んできて「チェコ侵入の時のソ連の様子を」とインタービューされた。ソ連にいた私は何も知らず、その新聞記者から教えてもらうという始末。
1968年という年は、世界中が自由を叫んでいた。輝いていて、ほとばしっていて、そして泣いているような潤んだ青春群像だ。
帰国して久しぶりに再会した藤本は学生運動のピークを迎え、多忙な暮らしの渦中の人だった。なにより驚いたのは、私がソ連に旅立った直後から夏いっぱい拘置所の中にいたらしい。私が旅立ったとき、彼は釈放されて出てきたばかりだったのに…。なんということかと呆然としてしまった。彼は特別そのことは言わずに、あいかわらずブラリと現れて消える。短い逢瀬があるだけだった。
言葉ではなにも伝わらない。別々の所に生きている距離感が私にはたまらなくて、一度別れを言い出したことがあった。藤本はただ「そうか」というだけで反論はしない。残ったのは淋しさだけで、たぶん、そばで見ると少し私は変になっていたのかもしれない。母がふっとこんなことを言った。「別れんといたほうがいいよ。あの人はあんたのお守りさんやから。別れたりしたらかえって心配で心配で」と。よく考えると不思議な発言ではある。拘置所のお世話にばかりなっているこの男がどうして私のお守りさんだというのか。でも、この母のひと言は効いた。私も心の平静を失っている自分を知っている。別れたくて別れを言い出したわけじゃなかった。電話をかけてまた逢うことが続き、そのまま10月21日を迎えた。
その日、彼は防衛庁へ行くデモの先頭に立つことになっていた。当然また逮捕だ。その深夜、東京はマヒ状態になった。新宿駅構内を学生が占拠し、駅前広場はヘルメットをかぶった学生で埋まった。私は一人でうろうろとmその騒然として燃えている学生を見て歩き、いまごろは捕まっているはずの彼のことを思っていた。学生の隣にいて、でも一緒にはなれない。あのころの私の孤独感だった。ただ一部始終をちゃんと見ていたい気持ちだけはあった。
ひとり家に帰り着き、ボーっとテレビを見ていたら電話がかかった。藤本からだ。「どうしてだか捕まらなかった。いまから帰る。タクシーの金たのむ」。警官隊とぶつかった時どんどん前の方につっこんでいるうちに警官の後ろ側に出ていたというわけだ。黙ってウイスキーをグラス一杯飲み干して、いつもと同じで、出来事をあまり語らず、ただ眠った。明日からは逃亡生活だ。この部屋で捕まったりしたらたいへんだし、逢うことも絶対できない。次の朝早く彼はどこかに行ってしまった。次の山場は11月7日と決まっていた。当然彼はその日も先頭に立つことになる。それは当然捕まることを意味していた。
忘れもしない11月6日の深夜。「またしばらく逢えへんからな」。突然訪ねてきた。朝までの短い逢瀬。ところがそこへ酔っぱらった一団がドヤドヤと訪ねてきたのだ。「フランスから持って帰ってきたこの歌、おトキにどうしても聞かせたくなってさあ。絶対これ日本でもヒットするよ。おトキ歌ったらあ」と。まあなんと情熱的なありがたくないお客だったろうか。しかたなく私はその連中と一杯やって、その歌というのを聞くことになった。それがメリー・ポプキンの「悲しき天使」だ。「すごくいい!」と思った。泣けてたまらなかった。「The were the days my Friend」「そんな日々があったよね」というリフレインを繰り返し聞きながら短い逢瀬も終わり、11月7日予定通り彼は逮捕された。「ほんの一カ月」のはずの拘留はクリスマスも正月もつづき、年を越した。あの時、あの歌はすべてを過去形で歌っていたのだ。「Once upon a time」。昔々私たちはそんな日々あったのだ、と……
学生が案内してくれたアパートには20人近くの学生がいて、そこにはチェコの人やハンガリーの人やいろいろな学生がまじっていた。自由で西欧的でどうもソ連が嫌いな人たちらしく、私に「この国の歌なんか歌わなくてもいい。あなたはあなた自身の歌を歌ったほうがいい。僕たちはこの国の歌なんか嫌いなんだ」と、しきりに言って、大きなテープレコーダーでヨーロッパの電波からキャッチした音楽をガンガンかけて踊ったり、一緒に歌ったりしていた。一番人気はビートルズよりもアニマルズらしい。おもしろかったのは東欧のロックだった。シンプルなマイナーコードで、シャウトにはアメリカのロックにはないスゴ味があって、いまでもその音が耳の底に残っている。
あれは過激な学生たちだったのか、それともごく普通の人たちだったのかはわからない。けれど私を案内してくれた学生のひとりとホテルに戻ったときには大事件になっていた。私が単独に許可なく行動したことは、とんでもないことだったのだ。その学生も平謝りに謝って、それからは何度か逢いに来たのに、許可されずに帰ってしまうことが続いた。モスクワへ私が行く頃には、彼らもみんなモスクワにいるから、その時、電話して逢おうと約束していたのに、結局どの電話も意味不明の混線をおこして切れてしまうという結果になった。
実のところ、私はなにも知らなかったし、彼らも知っていたかどうかわからないけれど、ちょうどその頃、チェコ侵入があったのだ。プラハに戦車が突入し、日本では大ニュースだったはず。ソ連国内での報道がどうだったかは知る由もない。船で横浜に帰国したとき、新聞記者がドカドカと乗り込んできて「チェコ侵入の時のソ連の様子を」とインタービューされた。ソ連にいた私は何も知らず、その新聞記者から教えてもらうという始末。
1968年という年は、世界中が自由を叫んでいた。輝いていて、ほとばしっていて、そして泣いているような潤んだ青春群像だ。
帰国して久しぶりに再会した藤本は学生運動のピークを迎え、多忙な暮らしの渦中の人だった。なにより驚いたのは、私がソ連に旅立った直後から夏いっぱい拘置所の中にいたらしい。私が旅立ったとき、彼は釈放されて出てきたばかりだったのに…。なんということかと呆然としてしまった。彼は特別そのことは言わずに、あいかわらずブラリと現れて消える。短い逢瀬があるだけだった。
言葉ではなにも伝わらない。別々の所に生きている距離感が私にはたまらなくて、一度別れを言い出したことがあった。藤本はただ「そうか」というだけで反論はしない。残ったのは淋しさだけで、たぶん、そばで見ると少し私は変になっていたのかもしれない。母がふっとこんなことを言った。「別れんといたほうがいいよ。あの人はあんたのお守りさんやから。別れたりしたらかえって心配で心配で」と。よく考えると不思議な発言ではある。拘置所のお世話にばかりなっているこの男がどうして私のお守りさんだというのか。でも、この母のひと言は効いた。私も心の平静を失っている自分を知っている。別れたくて別れを言い出したわけじゃなかった。電話をかけてまた逢うことが続き、そのまま10月21日を迎えた。
その日、彼は防衛庁へ行くデモの先頭に立つことになっていた。当然また逮捕だ。その深夜、東京はマヒ状態になった。新宿駅構内を学生が占拠し、駅前広場はヘルメットをかぶった学生で埋まった。私は一人でうろうろとmその騒然として燃えている学生を見て歩き、いまごろは捕まっているはずの彼のことを思っていた。学生の隣にいて、でも一緒にはなれない。あのころの私の孤独感だった。ただ一部始終をちゃんと見ていたい気持ちだけはあった。
ひとり家に帰り着き、ボーっとテレビを見ていたら電話がかかった。藤本からだ。「どうしてだか捕まらなかった。いまから帰る。タクシーの金たのむ」。警官隊とぶつかった時どんどん前の方につっこんでいるうちに警官の後ろ側に出ていたというわけだ。黙ってウイスキーをグラス一杯飲み干して、いつもと同じで、出来事をあまり語らず、ただ眠った。明日からは逃亡生活だ。この部屋で捕まったりしたらたいへんだし、逢うことも絶対できない。次の朝早く彼はどこかに行ってしまった。次の山場は11月7日と決まっていた。当然彼はその日も先頭に立つことになる。それは当然捕まることを意味していた。
忘れもしない11月6日の深夜。「またしばらく逢えへんからな」。突然訪ねてきた。朝までの短い逢瀬。ところがそこへ酔っぱらった一団がドヤドヤと訪ねてきたのだ。「フランスから持って帰ってきたこの歌、おトキにどうしても聞かせたくなってさあ。絶対これ日本でもヒットするよ。おトキ歌ったらあ」と。まあなんと情熱的なありがたくないお客だったろうか。しかたなく私はその連中と一杯やって、その歌というのを聞くことになった。それがメリー・ポプキンの「悲しき天使」だ。「すごくいい!」と思った。泣けてたまらなかった。「The were the days my Friend」「そんな日々があったよね」というリフレインを繰り返し聞きながら短い逢瀬も終わり、11月7日予定通り彼は逮捕された。「ほんの一カ月」のはずの拘留はクリスマスも正月もつづき、年を越した。あの時、あの歌はすべてを過去形で歌っていたのだ。「Once upon a time」。昔々私たちはそんな日々あったのだ、と……

