2003年 冬 南米への旅
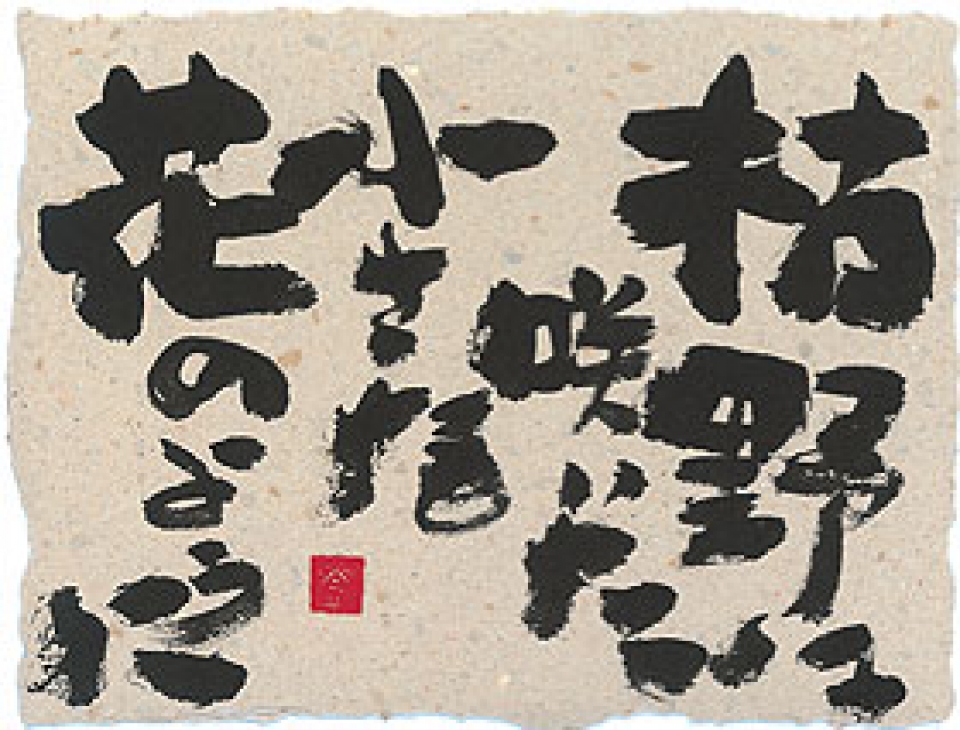
歌手活動を再開した一九七三年秋、偶然に長谷川きよしさんと出逢う機会があった。その時、きよしさんが「ふたつの顔」シリーズということでいろんな人とジョイントコンサートをしているので、何かやってみないかという提案をしてきた。
結婚、出産を経て、フォルクローレやいろんな民族音楽のテイストに魅惑されていた私は、すぐこの話に乗り、きよしさんとのデュエット曲づくりを模索しはじめた。
ブラジルのサンバ、そしてペルー、アルゼンチンのフォルクローレ、ちょっとアラブ風の曲など、きよしさんと私、それぞれから曲を出し合い、ひとつのコンサートをつくっていく……。
これまでにないほど二人の重なり合うコンサートを目指すことになった。
二人がハーモニーをとると、音域がぐっと広がり、幅とふくらみが出る。これは大きな発見だった。
秋、いよいよリハがはじまり、詞が生まれ、曲が見えてくる。
そんな中で、何ともいえない不思議なエレガンスを発散するウニャ・ラモスの「灰色の瞳」にスタッフの人気が集まって来た。
もともとケーナのソロ曲だったので、詞はついていない。私はこの曲の漂うような淋しさ、恋しさ、懐かしさを絵に描くように詞を作った。
こういう風にいい気持ちになった時の私はすごく仕事が早い。
今も、一語一語を思いついた経過が思い出せない程、多分あっという間に作ったような気がする。
コンサートではこの曲だけアンコールでも歌うなど、強い人気が後にも残り、一気にレコーディングということになった。
忘れもしない、一九七四年一月、お正月明けの仕事始めとしてこの曲のレコーディングをし、その足で私は南米へと旅発ったのだった。
美亜子が一歳の誕生日をすませ、ぐっと大きくなったような気がして、母に一ヶ月あまりの育児を託していく決心をしたのだ。
私が、というよりは母が決心してくれた、といった方がよいのかもしれない。
食の細い美亜子は、風邪もひきやすく、楽な子供じゃなかったから、さぞや大変だっただろうなと、今頃になって母に頭を下げたくなる。
それほどまでして何で行くことになったのか。それには多少の経過があった。
はじめは、私たちのバンド全員で家族もみんな連れて、旅芸人のキャラバンのような形で南米を歩いてみようよ、という夢だった。
なんて素敵な企画なんだとみんなノリノリになり、メキシコ、ペルー、ボリビア、アルゼンチンとコースも考え、これをテレビ番組かなんかにしてバーンと放送したら「灰色の瞳」のパブリシティーにもなるし、新しく生まれ変わったTOKIKOのイメージアップにもなる! いいじゃない!?
こういう素晴らしいアイデアというものは、描いている時はあんまり素晴らしいので実現しないはずがないと思えてくる。
ところが、熱に浮かされるのは私たちばかり、徐々に現実が見えて来て、「スポンサーは誰なのか」「どこの局が番組にするのか」ということになり、あっという間にこの企画は消えていくことになった。
困ったのは私の気持ちと盛り上がってしまった夢の未来像。
スゴロクと同じ。このポイントを通れば次に進めるとわかった時、もう引き返すわけにはいかないのだ。
結局、せめて私ひとりでも行ってくるしかないだろうということになり、ついに旅発った。
メキシコでは「ペーニャ」と呼ばれるライブハウスに飛び入りで歌い、いろんなアーティストと知り合いになって、コンサートにまでゲスト出演するという思いがけない展開となったし、ペルーでは天野博物館の天野先生と出逢い、クスコ、マチュピチュはもちろん、チャンカイの遺跡にまで足を運び、おまけにリマで突然のコンサートまで開いた。
ボリビアでは沖縄から移民した島袋さんのジープでティアワナコの遺跡とチチカカ湖へ行き、大雨のために橋のない川で立ち往生するという経験もした。
アルゼンチンでは、たったひとり西側のインディオ地帯を車で走り、ウマウアカでの熱っぽい一夜を知り、ブラジルのリオではカーニバル前のファベーラの興奮を味わった。
「ひとり寝の子守唄」「知床旅情」といった淋しい歌の世界から、もっと躍動出来る音楽への脱出を願っていた私には、本当に大きな旅だった。フォルクローレやサンバがこの時代、最も新鮮で熱気あるものに思えたし、実際このころの南米は実に生き生きしていた。
帰国した時、空港に来ていた美亜子が歩いていたのにはびっくりし、ありがたくて泣いてしまったが、今考えても、行っておいてよかった!素晴らしい旅だったと心底思う。
「灰色の瞳」も思いがけず順調に売れて、もちろんビッグヒットにはならないが、じわりと音楽ファンの中にフォルクローレブームをつくることになった。
ウニャ・ラモスが来日し、大人気となり、その年の夏の長谷川きよしとの日比谷野音は七千人以上を集める大成功を遂げた。
決して明るくはないのに、太陽を感じさせてくれるフォルクローレの不思議さ、せつなくて悲しくて胸が熱くなる音楽のフェロモンなのだろうか。
私の心のカレンダーと時代のカレンダーが偶然交叉した、そんな風にも思える。
結婚、出産を経て、フォルクローレやいろんな民族音楽のテイストに魅惑されていた私は、すぐこの話に乗り、きよしさんとのデュエット曲づくりを模索しはじめた。
ブラジルのサンバ、そしてペルー、アルゼンチンのフォルクローレ、ちょっとアラブ風の曲など、きよしさんと私、それぞれから曲を出し合い、ひとつのコンサートをつくっていく……。
これまでにないほど二人の重なり合うコンサートを目指すことになった。
二人がハーモニーをとると、音域がぐっと広がり、幅とふくらみが出る。これは大きな発見だった。
秋、いよいよリハがはじまり、詞が生まれ、曲が見えてくる。
そんな中で、何ともいえない不思議なエレガンスを発散するウニャ・ラモスの「灰色の瞳」にスタッフの人気が集まって来た。
もともとケーナのソロ曲だったので、詞はついていない。私はこの曲の漂うような淋しさ、恋しさ、懐かしさを絵に描くように詞を作った。
こういう風にいい気持ちになった時の私はすごく仕事が早い。
今も、一語一語を思いついた経過が思い出せない程、多分あっという間に作ったような気がする。
コンサートではこの曲だけアンコールでも歌うなど、強い人気が後にも残り、一気にレコーディングということになった。
忘れもしない、一九七四年一月、お正月明けの仕事始めとしてこの曲のレコーディングをし、その足で私は南米へと旅発ったのだった。
美亜子が一歳の誕生日をすませ、ぐっと大きくなったような気がして、母に一ヶ月あまりの育児を託していく決心をしたのだ。
私が、というよりは母が決心してくれた、といった方がよいのかもしれない。
食の細い美亜子は、風邪もひきやすく、楽な子供じゃなかったから、さぞや大変だっただろうなと、今頃になって母に頭を下げたくなる。
それほどまでして何で行くことになったのか。それには多少の経過があった。
はじめは、私たちのバンド全員で家族もみんな連れて、旅芸人のキャラバンのような形で南米を歩いてみようよ、という夢だった。
なんて素敵な企画なんだとみんなノリノリになり、メキシコ、ペルー、ボリビア、アルゼンチンとコースも考え、これをテレビ番組かなんかにしてバーンと放送したら「灰色の瞳」のパブリシティーにもなるし、新しく生まれ変わったTOKIKOのイメージアップにもなる! いいじゃない!?
こういう素晴らしいアイデアというものは、描いている時はあんまり素晴らしいので実現しないはずがないと思えてくる。
ところが、熱に浮かされるのは私たちばかり、徐々に現実が見えて来て、「スポンサーは誰なのか」「どこの局が番組にするのか」ということになり、あっという間にこの企画は消えていくことになった。
困ったのは私の気持ちと盛り上がってしまった夢の未来像。
スゴロクと同じ。このポイントを通れば次に進めるとわかった時、もう引き返すわけにはいかないのだ。
結局、せめて私ひとりでも行ってくるしかないだろうということになり、ついに旅発った。
メキシコでは「ペーニャ」と呼ばれるライブハウスに飛び入りで歌い、いろんなアーティストと知り合いになって、コンサートにまでゲスト出演するという思いがけない展開となったし、ペルーでは天野博物館の天野先生と出逢い、クスコ、マチュピチュはもちろん、チャンカイの遺跡にまで足を運び、おまけにリマで突然のコンサートまで開いた。
ボリビアでは沖縄から移民した島袋さんのジープでティアワナコの遺跡とチチカカ湖へ行き、大雨のために橋のない川で立ち往生するという経験もした。
アルゼンチンでは、たったひとり西側のインディオ地帯を車で走り、ウマウアカでの熱っぽい一夜を知り、ブラジルのリオではカーニバル前のファベーラの興奮を味わった。
「ひとり寝の子守唄」「知床旅情」といった淋しい歌の世界から、もっと躍動出来る音楽への脱出を願っていた私には、本当に大きな旅だった。フォルクローレやサンバがこの時代、最も新鮮で熱気あるものに思えたし、実際このころの南米は実に生き生きしていた。
帰国した時、空港に来ていた美亜子が歩いていたのにはびっくりし、ありがたくて泣いてしまったが、今考えても、行っておいてよかった!素晴らしい旅だったと心底思う。
「灰色の瞳」も思いがけず順調に売れて、もちろんビッグヒットにはならないが、じわりと音楽ファンの中にフォルクローレブームをつくることになった。
ウニャ・ラモスが来日し、大人気となり、その年の夏の長谷川きよしとの日比谷野音は七千人以上を集める大成功を遂げた。
決して明るくはないのに、太陽を感じさせてくれるフォルクローレの不思議さ、せつなくて悲しくて胸が熱くなる音楽のフェロモンなのだろうか。
私の心のカレンダーと時代のカレンダーが偶然交叉した、そんな風にも思える。

