2006年 春 ふたつの歯車
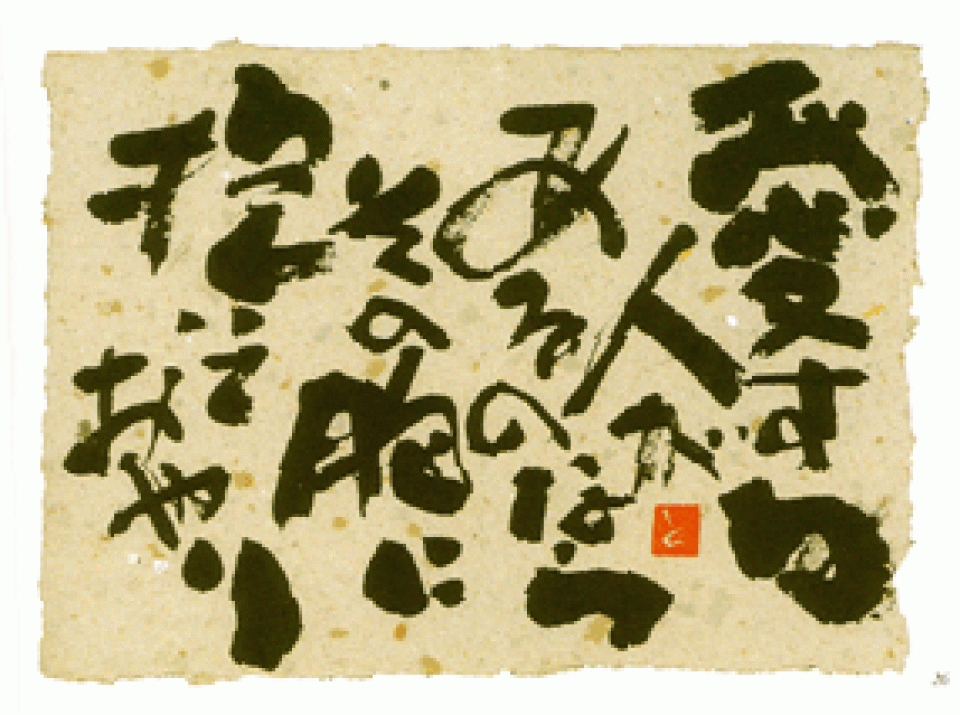
歌が生まれる瞬間の記憶は何か不思議だ。
漂流する船のように不確かな時間の中をゆらゆらしているうちに、ふいに詩が形になって立ち現れてくる。
「愛する人があるのなら」
この歌の詩が出て来た時のことは何故かその不思議さも含めてはっきりと記憶している。はじめは恋人の浮気を知ってしまった時の女の気持ちを歌にしようとしていた。
「いいじゃない、愛してあげれば」
そんな風にさらりと男にむかって言える女がいてもいい。
クールで格好よく、でもせつなく辛い、そんな女。
でも、この一行にメロディがつき、次の行が見えて来るうちに、いつの間にか女自身が誰かを恋する気持ちにのめり込んで行く時の真情あふれる歌になっていた。私自身の体をくぐり抜けるように、言葉が一気に三番までの歌詞になり、「愛したい」という気持ちが体の奥底から突き上げて、気づいたら涙でびしょぬれって感じになっていた。
歌をつくりながら泣いてしまうことはめずらしいことではないけれど、あの時のことはとてもよく覚えている。暗くした食堂のテーブルで家族がみんな寝静まった夜中だった。「歌が出来た」といううれしい気持ちと突き上げて来た感情に、しばらくぼうっとしていた。
あの一時期、藤本との愛に行き詰まり感があって、別れたら楽だろうなというようなことも考えたことがあった。
だからといって、誰か別の恋人が欲しいというんじゃない。
もっとちゃんと愛したいのに、何故かうまく愛せてない自分自身に苛立っていたのだ。
ステージの上でこの歌を歌いながら、やっぱり泣けた。「あー、これが私だ」と叫びたいような気持ちになるのだ。
でも日常に帰ると、その反対になってしまう自分がいる。
「うまくやれない、と悩むってことは、うまくやりたい、と強く願っているってことでしょ」と、その時のマネージャーに言われたのを思い出す。
一九七八年、夫、藤本は株式会社「大地」の切りもりに必死。
三月に、中島みゆきの「この空を飛べたら」が発売になったこの年は、私にとってもめっぽう忙しい年だった。
二人の娘の子育てと仕事のやりくりに七転八倒、演奏旅行に出かけ、テレビに出演し、歌をつくり、レコーディングをする。私のこんな忙しさにさぞや夫も辟易していたことだろう。
幸い、「別れる」などということにもならず、彼は彼、私は私でそれぞれの歯車をそれぞれの想いでまわしていたのだ。
この年の夏、この「愛する人があるのなら」を含むオリジナル五曲と、「この空を飛べたら」や「アナック」などの五曲を収録した『愛する人へ』というアルバムを伊豆のスタジオでレコーディングした。
こんな時は母にも同行してもらって、伊豆の宇佐美の家に娘二人と泊まりこみ、伊豆高原のスタジオに通うのだ。
告井延隆のプロデュースで、センチメンタル・シティ・ロマンスのメンバーとのレコーディングはすごく新鮮で、充実した楽しい雰囲気ですすんでいた。小さな娘たちがスタジオで遊んでいたりする姿も結構悪くない。
レコーディングのあったこの夏の終わりには「アナック(息子)」の作曲者であるフレディ・アギラに逢うためにフィリピンまで出かけている。
一方で、長谷川きよしさんとのジョイントコンサートでは、徹底的に全国をまわっていた。
中でも奥尻島の漁港で行った野外コンサートは思い出深い。
私たちが楽屋に使った民宿が、その後の大津波で大破してしまった「洋々亭」だったことも感慨深い。コンサートには島の老若男女が集まり、格好いい漁師のおっさん達は、サンバだって何だってソーラン節の乗りで迫力満点!もちろん打ち上げは、帆立やアワビやウニの大宴会だ。
夏だけでもこんな風にめくるめく思い出がいっぱい。七八年はまさに豊漁の年だった。
子連れの歌手業は確かに大変だったけれど、それも得難い思い出。
女心の揺れもあってあたりまえ。私はまだ三十代半ばだったのだ。
漂流する船のように不確かな時間の中をゆらゆらしているうちに、ふいに詩が形になって立ち現れてくる。
「愛する人があるのなら」
この歌の詩が出て来た時のことは何故かその不思議さも含めてはっきりと記憶している。はじめは恋人の浮気を知ってしまった時の女の気持ちを歌にしようとしていた。
「いいじゃない、愛してあげれば」
そんな風にさらりと男にむかって言える女がいてもいい。
クールで格好よく、でもせつなく辛い、そんな女。
でも、この一行にメロディがつき、次の行が見えて来るうちに、いつの間にか女自身が誰かを恋する気持ちにのめり込んで行く時の真情あふれる歌になっていた。私自身の体をくぐり抜けるように、言葉が一気に三番までの歌詞になり、「愛したい」という気持ちが体の奥底から突き上げて、気づいたら涙でびしょぬれって感じになっていた。
歌をつくりながら泣いてしまうことはめずらしいことではないけれど、あの時のことはとてもよく覚えている。暗くした食堂のテーブルで家族がみんな寝静まった夜中だった。「歌が出来た」といううれしい気持ちと突き上げて来た感情に、しばらくぼうっとしていた。
あの一時期、藤本との愛に行き詰まり感があって、別れたら楽だろうなというようなことも考えたことがあった。
だからといって、誰か別の恋人が欲しいというんじゃない。
もっとちゃんと愛したいのに、何故かうまく愛せてない自分自身に苛立っていたのだ。
ステージの上でこの歌を歌いながら、やっぱり泣けた。「あー、これが私だ」と叫びたいような気持ちになるのだ。
でも日常に帰ると、その反対になってしまう自分がいる。
「うまくやれない、と悩むってことは、うまくやりたい、と強く願っているってことでしょ」と、その時のマネージャーに言われたのを思い出す。
一九七八年、夫、藤本は株式会社「大地」の切りもりに必死。
三月に、中島みゆきの「この空を飛べたら」が発売になったこの年は、私にとってもめっぽう忙しい年だった。
二人の娘の子育てと仕事のやりくりに七転八倒、演奏旅行に出かけ、テレビに出演し、歌をつくり、レコーディングをする。私のこんな忙しさにさぞや夫も辟易していたことだろう。
幸い、「別れる」などということにもならず、彼は彼、私は私でそれぞれの歯車をそれぞれの想いでまわしていたのだ。
この年の夏、この「愛する人があるのなら」を含むオリジナル五曲と、「この空を飛べたら」や「アナック」などの五曲を収録した『愛する人へ』というアルバムを伊豆のスタジオでレコーディングした。
こんな時は母にも同行してもらって、伊豆の宇佐美の家に娘二人と泊まりこみ、伊豆高原のスタジオに通うのだ。
告井延隆のプロデュースで、センチメンタル・シティ・ロマンスのメンバーとのレコーディングはすごく新鮮で、充実した楽しい雰囲気ですすんでいた。小さな娘たちがスタジオで遊んでいたりする姿も結構悪くない。
レコーディングのあったこの夏の終わりには「アナック(息子)」の作曲者であるフレディ・アギラに逢うためにフィリピンまで出かけている。
一方で、長谷川きよしさんとのジョイントコンサートでは、徹底的に全国をまわっていた。
中でも奥尻島の漁港で行った野外コンサートは思い出深い。
私たちが楽屋に使った民宿が、その後の大津波で大破してしまった「洋々亭」だったことも感慨深い。コンサートには島の老若男女が集まり、格好いい漁師のおっさん達は、サンバだって何だってソーラン節の乗りで迫力満点!もちろん打ち上げは、帆立やアワビやウニの大宴会だ。
夏だけでもこんな風にめくるめく思い出がいっぱい。七八年はまさに豊漁の年だった。
子連れの歌手業は確かに大変だったけれど、それも得難い思い出。
女心の揺れもあってあたりまえ。私はまだ三十代半ばだったのだ。

