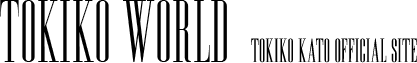Tokiko Now
01.
ボブ・ディランが、ウディ・ガスリーを信奉し、ピート・シガーとの出会いからキャリアをスタートさせたことはよく知られている。でもどうしてディランがピートと離れていったのか、その詳しい経緯をずっと知りたいと思っていた。この映画は、そのテーマを真っ直ぐ取り上げている。

私がピート・シガーに深く興味を抱いたのは、2012年の春、ニューヨークを訪れ、ピートの住んでいる街まで行ったことがきっかけだった。それというのも、2011年3月11日の東日本大震災で福島第一原発が爆発事故を起こしたことから、ニューヨークから近いインディアン・ポイントという原発の立地する街にピートが住んでいること、この原発を批判し監視ている人たちのその運動の中に、彼が参加していることがわかったからだった。
ここはあのウッドストックからも近く、そこを見たいという思いもあって、ニューヨークの友人と一緒に出かけた。
残念ながら、その時、この映画にも登場しているピートの妻のトシさんが重篤な病気で、一歩もそばを離れない彼と会うことはできなかった。でも戦前からアメリカに渡った日系アメリカ人の女性が彼のパートナーであることを知り、ますます親近感を覚えたのだった。
もちろんもう一つの関心は「花はどこへ行った」の歌詞が、ロシアの文豪、ショーロホフの小説「静かなドン」の中に出てくるコサックの子守唄が元になっていることでもあった。
1955年にふとポケットからその歌詞をメモった3行の詩をもとにこの歌を彼は作ったという。それから約10年ほど過ぎてから、キングストントリオが勝手にこの歌を歌っていたことから、彼が名乗りをあげピートの曲とわかった、そんな面白い経緯がある。
このことはピート自身が書いた「虹の民におくる歌」という本に詳しく書かれている。

この本は彼の全人生がわかると言ってもいい本だけど、この本の中に、ボブ・ディランとの出会いは一切触れられていない。この映画の軸になっている「ニューポート・フォークフェスティバル」についてはいっぱい書かれているのに、、。
それだけに、ピートがボブ・ディランと何があったか、どう見ているのか、一切わからない。
この本の冒頭の章にあるひとつの言葉が、辛うじてその気持ちを表しているのかもしれない。
「ステージでアコースティックギターを持ってマイクの前に立ち、作りたてほやほやの歌を歌うのがフォークシンガーだというのは間違った言葉の使い方だ」(概略)と書いている。
この映画でボブ・デイランが次々と新曲を歌い、果てはエレキギターを持ってきて、大音量のバンドで歌うことでピートとぶつかってしまうシーンが描かれていた。
ピートがディランを説き伏せるように語った言葉が心に残る。
「みんな、一人一人が小さなスプーンで砂を掬い、大きな石が括られた天秤棒の反対に吊るされた空っぽの袋に入れていく。いつかその袋が重くなって、大きな石を持ち上げられるようになることを願ってね。君はそこに大きなシャベルを持ってやってきたようなものだ。」(概略)
創世記のアメリカ人が歯を食いしばるように築いてきた文化、多くは遠いヨーロッパから移民たちが持ち寄ったものだった。その深い地層から湧き起こる歌を掘り起こしてきたウディー・ガスリー、ピート・シガーの時代から、生まれたばかりの歌がレコードになりテレビで放送されて大人気を博す、商業主義の時代へと劇的に変わる、それをこの映画が描こうとしたのではないか。
日本にも、ほんの短い時間だったけれど、これに近い動きがあった。1960年代後半、新宿西口駅で開かれていたフォークゲリラのアンダーグラウンドの集会などで生まれたシンガーソングライターの波が、ニューミュージックとなってその後の音楽業界のドル箱になっていった歴史の中に。
アメリカの大統領が変わっただけで、世界が振り回されている日々。アメリカがどこからきてどこへ行こうとしているのか、大きな岐路に立たされている今だからこそ、何か感慨深いものがある。